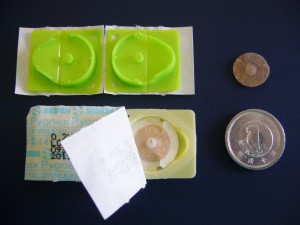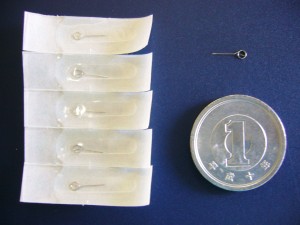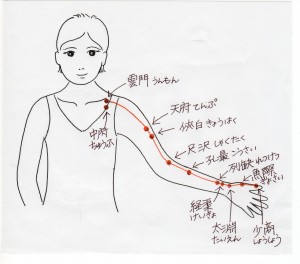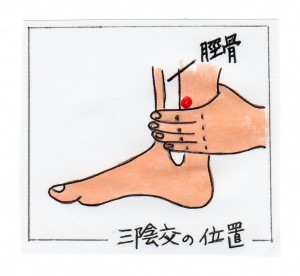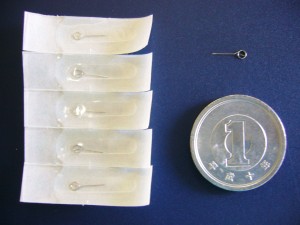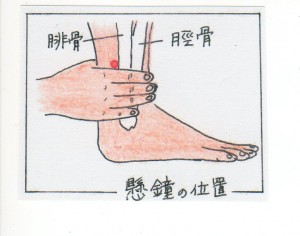鍼とお灸の手法~その1
先日、ブドウを食べているときに、妙なことに気づきました。
体の右側に、ブドウの入ったお皿があるのに、
わざわざ左手でブドウを食べていました。
コトーは右利きで、ブドウは右手に近いのに…。
何で?
実は似たようなことを、以前にも感じました。
大型のカッターを扱っていたとき、
誤って左の人差し指の腹をカッターでグサリッ…。
痛くて、しばらくは左の人差し指が使えませんでした。
そのとき、日常生活で一番困ったことは何だと思いますか?
化粧です。
コトーは、リキッド・タイプ(液体)のファンデーションを使っています。
一般的には、パフにファンデーションをつけ、
それを使って顔にファンデーションをのせますね。
面倒臭がり屋のコトーは、左人差し指と中指の腹に
直にファンデーションをつけて、
それを顔に塗りたくります。
けがをしたときに、そのことに気づきました。
利き手の右手ですると、とてもぎこちない…。
何で?
携帯電話は左で持ちながら、左で操作します。
利き手は使わず、反対の手だけで操作することもあるんだなぁ~。
『こんなときには利き手で操作し、
こーんなときには反対の手で操作する。』
コトーの脳にそんな法則性があるのか…。
ここ数日間、自分の両手の使い方を観察していました。
しかし…、分からない。
法則性を見つけられたら、ご報告します!!!
(って、誰も知りたくないかな~?)
左の人差し指をけがしたとき、
意外にも仕事(鍼灸)に支障をきたしませんでした。
左の人差し指の代わりに左の中指が大活躍!
仕事によって、とーっても大事な指と、
代わりの効く指があるんですね。
ところで、皆さんは鍼やお灸を受けたことがありますか?
では、鍼やお灸をしているところを見たことはありますか?
今日は、鍼のやり方を写真付きでご紹介します!
おーっ、前置きが長すぎた…。 しっつれーい!
鍼とお灸は中国から伝わりました。
中国では鍼を直に手で持ち、ツボに刺します。
日本では鍼管(しんかん)に鍼を入れてツボに刺します。






これは『片手挿管 かたてそうかん』という手法で、
片手だけで鍼管に鍼を入れて、ツボに置きます。
ちょっと練習が必要です。


鍼管よりも鍼のほうが数ミリ長く作られています。

鍼管の先端まで鍼が入ったら、
鍼管を引き上げて取ります。

鍼はすぐ抜くときもあれば、
ちゅんちゅんちゅんと軽くつつくように刺激することもあれば、
数十分間、鍼を置くこともあります。
皆さん、鍼は怖いですか?
鍼管を使うことによって、
鍼がツボに入るときの感覚がやわらぎます。
鍼は即効性があるなぁ~と、よく思います。
気になる方は、ぜひチャレンジしてほしいです!!!