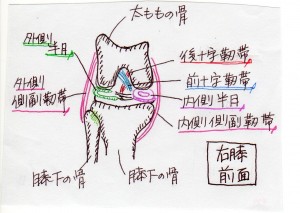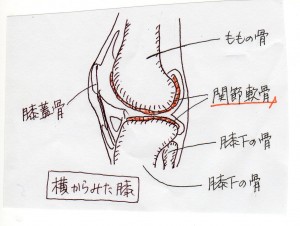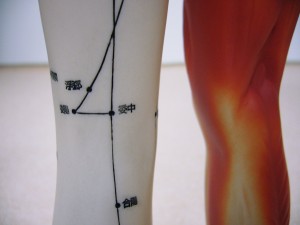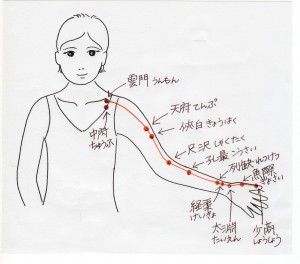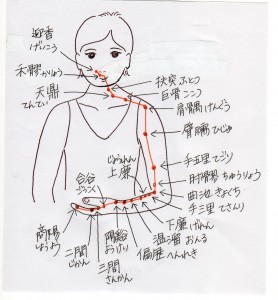中国留学思い出し日記~七星針
日本ではなかなかお目にかからない鍼、七星針。
18.5cmの柄の先には、
長さ4mmの鍼が7本植え込まれている。
柄の端を持ち、
こんなふうに柄をしならせて、
皮膚をリズミカルに弾くように叩きます。
留学先の中国では、皮膚病や顔の筋肉の麻痺に対して、使っていました。
顔の皮膚はとてもデリケートなので、
おでこ・目の周り・頬・口の周りを、熟練した中国人鍼灸師がしても、
七星針はかなり痛い。
若い女性は、涙を流しながら…、
男性でも痛さでつい顔をそむけながら…、
それでも毎日通われていました。
中国人女性はがまん強い!
日本ではこうはいかない。
当鍼灸院でもこの鍼は使っていません。
*
*
さてさて、こんな話をした後、
「鍼の良さ」を書くぅ~?!?!?!
前回書ききれなかったので、踏ん張ります!
一番の良さは『即効性』でしょうか。
ガチガチな筋肉の痛みや頭痛、内臓の痛みなどの不調など、
すすっと改善しやすい。
もちろん、長期間に渡って症状のある場合は、
時間がかかる時もあります。
*
『刺激の強弱ができる』のもいいですね。
「即効性=ガツッと打つ」というイメージがあるかも知れませんが、
一人ひとりの症状・体調・体質を見極めて、
鍼の太さ・長さ・刺し方を選びます。
*
『ピンポイントにアプローチできる』のも鍼ならでは。
肩や膝の痛みで治療を続けていると、、
筋肉の中に硬いスジが残ることが多い。
このスジを鍼で緩めると、筋肉全体が和らいで、痛みがぶり返しにくい!
手の腱鞘炎で〇〇筋(筋肉の名前)を緩めることも、
お尻の奥の奥の〇〇筋を緩めることもできる!
*
『刺す部位にあわせることができる』
例えば、片頭痛では、痛みが出ているコメカミの皮膚と水平に…、
肩甲骨一面にぺたっとついている筋肉に対しても皮膚と水平に…。
皮膚に垂直に刺したら、すぐ頭蓋骨や肩甲骨の骨にあたってしまうから。
*
『遠隔操作』できるのは、あらゆる治療方法の中では
珍しいでしょうね。
昔から、上半身の病は下半身で、
下半身の病は上半身のツボを使って治す!と言われています。
*
『ヒトの体と相性がいい』
年季の入ったガチガチコチーンの筋肉は、
鍼を跳ね返そうとするくらいに頑固!
そんなときは筋肉の表面に鍼が触れるくらいで待機。
池や川に小石を投げた時の波紋のように、
鍼を刺したところを中心に少しずつ輪を描くように
筋肉が緩んでくる…。
(これは鍼の取っ手を持つ私の感触)。
そうなると、筋肉にお伺いを立てて、
もう少し皮膚の中まで、鍼を無理なく入れることができる。
*
まだまだ若輩者の鍼灸師がえらそうに、鍼のことを語り、
すみませ~ん。
でも、鍼について熱く語れるようになった自分がうれしいなぁ~。
3回続けて鍼に関するブログとなりましたが、
目を傾けて(?)いただき、ありがとうございます。