動画撮影、裏話。
動画の台本を書いてみた。長い。長すぎる。文章を書き始めると、なぜ長くなるのか。これなら、動画にするよりもブログにのせたほうがいい。一番、何を伝えたいのか。台本を削る。削る。削る。
台本を覚える間もなく、リハーサル。手元だけを撮影するから、台本を読みながら撮れると思いきや、鍼やお灸を扱うので手元から視線を外せない。そうなると、台本通りに簡潔には話せない。うー!うー!うー!
なんとか撮影していると、「カー!カー!カー!」軽快なカラスの鳴き声。トラックが通りすぎる音。様々な音に撮影は中断。事前に音声だけを録音し、本番ではそれを流しながら撮影することになった。撮影中は鍼やお灸の操作だけに集中できるから、撮影もスムースにいくはず!
台本の中身をかなり削ったにもかかわらず、リハーサルでは撮影時間が長かった。更に削る。削る。よしっ!音声を録音しよう!

何度か台本を読んでから収録!と思いきや、録音する場所は変わらないから、カラスは鳴き、車は走り抜ける。よしっ!早朝に録音しよう!
静まり返った朝。何度も台本を読み、声の調子を整える。よしっ!録音だ!快調に録音していると、「チーチチチチ」鳥のさえずり。普段なら「風流だねぇ~」と思うが、この状況では「随分長くささやいてるなぁ」としびれを切らす。
録音した音声をその場で聞いてみる。「鍼は…」の冒頭の「は」が聞き取りにくい。中学・高校の部活『コーラス部』を思い出す。おなかから声を出すことが肝心だ。よしっ!立って録音しよう!
おっ?!声量が増えたのか聞き取りやすくなった。7年ほど前、テレビやラジオの取材を受けたことがある。テレビなどから流れる自分の声にがっかりした。小さい頃から鼻声だったが、まるっきり変わっていない。しかし、今回はそれを感じない。ここ数年、鼻の通りがいいから???
録音した音声を何度もチェック。もうちょっとゆっくり話そうかな。○○を強調して話そうかな。工夫したくなる。そういえば、小学校の頃、人形劇部に所属し、体育館で発表会があった。童話「雪の女王」で少女ゲルダの声を担当した。あの時も、こんな風に練習したんだなぁ…。何度も音声を撮り直していたら、のどが痛くなってきた。これでよしとしよう。
動画の冒頭のあいさつは自分の顔も映るから、録音した音声は使えない。撮影までにセリフを覚えるぞ。散歩中、トイレの中、お風呂の中、どこでもセリフの稽古。中学1年生の時、ちょこっと演劇部に所属してたけどねぇ…。1本の動画のあいさつは1分もないけれど、10本ともなるとセリフがごちゃごちゃになる。よしっ!
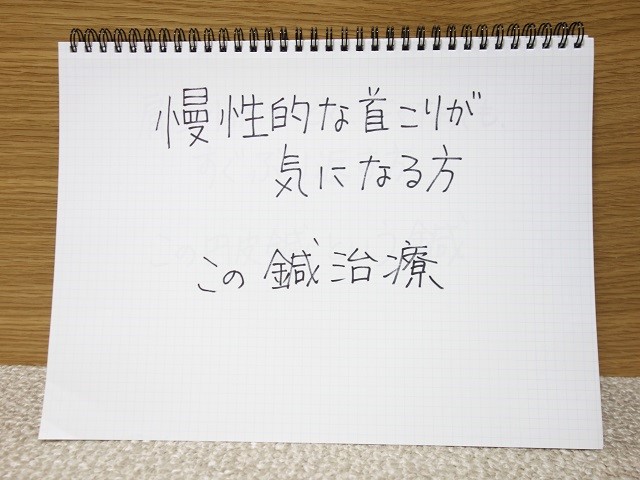
カメラの隣でモデルさんにカンニングペーパーを持ってもらおう。
撮影当日、カメラマンに言われた。「コトーさん、眼鏡のレンズにライトが反射してるから眼鏡を外しましょう」。えーっ、えーっ、えーっ。眼鏡を外したらド近眼のコトーは、せっかく作ったカンニングペーパーが読めない。しかし、あらゆる所でセリフの稽古をしていたおかげか、とちることはほとんどなく、10本の撮影を1日で終えた。終了後、ヘロヘロだったけど。
コトーはSNSが大の苦手。You Tubeに関する本を読みあさり、ネットで情報を集め、You Tubeチャンネルをなんとか立ち上げ、必要なことをなんとか書き込み、10本の動画をなんとか載せることが出来た。1本はホームページの『オンライン教室ページ』にも載せ、残りの9本は『鍼灸治療ページ』の『鍼灸の手技』にある。昨年、ブログで鍼とお灸の手技を書いたけれど、映像で見るとより理解してもらえると思う。東洋医学や鍼、お灸に興味がある方はぜひ見てほしい。
おととい、昨日と動画三昧でした。おつきあいいただき、ありがとうございます!福岡市南区にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の鍼灸師・理学療法士・ユーチューヒャーのコトーでした。



