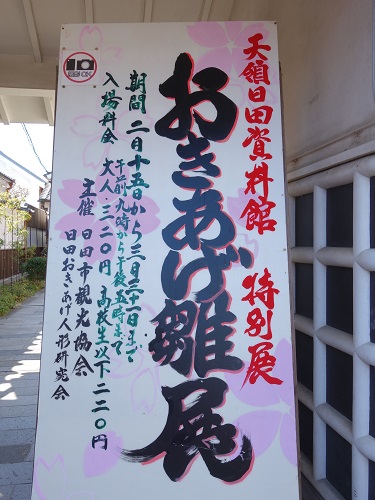2023年春!舞鶴公園の桜をテ~クテ~ク散策!
福岡市にある、舞鶴公園へ花見に出かけた。

以前、撮った福岡城跡。
1600年、黒田長政は、関ヶ原の戦いの功績で、筑前52万石の大名となった。福岡藩初代藩主となり、1601年から7年の歳月をかけて、福岡城を築き上げた。
福岡は海に面している。海側から城を望むと、鶴が羽ばたく姿と似ていたので、『舞鶴城』とも呼ばれていた。
現在、天守閣などの城は残っていない。総延長3㎞を超える石垣が残っている。石垣の高さは10m以上のところもある。

石垣の角は『算木積み (さんきづみ)』という手法が使われ、石垣の強度がアップする。今から420年ほど前、重機がない時代に、人力でこれほど精巧な角のラインを造るとは!ご先祖様、素晴らしい!
舞鶴公園は、その城内にあり、約500本の桜が植えられている。

晴天下では、新緑もまぶしい。ゆるやかな坂を上ると、石垣の上に出た。

先ほどの新緑は紅葉だったのねぇ~。更に、城内を歩くと…。おーっ!

年季の入った桜が連なる。おっ?近づくと…。

幹がねじれてる!若く細かった幹が『横に倒れては戻る』を繰り返しながら成長したのかなぁ…。幹の間から、赤ちゃん枝が育ってる。

背の高い、しだれ桜。

桜餅ってピンク色だけど、桜の花びらは意外と白に近い。

しだれ桜の中には、濃いピンク色もあり、青空に際立つねぇ~。更に、城内を歩き、石段を上り、一番高い所から眺めると…。

福岡城跡の向こうは、ビルやマンション。黒田長政は天守閣から、ビル群の背後にある、海を眺めていたんだろうなぁ…。
花見を堪能した後は、街中をテクテクテク。あっ!

花が桜に似ているけれど桜じゃない。何という名前だったか、うーっ、思い出せない。

あっ!更に濃いピンク色。もちろん、花の名前は…、知らない。
時間に余裕があるときは、公共の交通機関を使わずに、徒歩で移動する。こんな風に、元気いっぱいの花たちに巡り合えるのは、散歩の楽しみ。体力や筋力の維持にもなる。そして、目的がもう1つ。
もし、外出先で大地震などの大災害にあい、電車やバスがストップし、携帯電話などの通信機器も使えなかったら…。歩いて自宅まで帰れるように、ルートを覚えている。しかし、コトーの方向音痴はひどい!
18年ほど前の話。車を運転して、高速で北九州まで行こうとした。右手の福岡空港を超えて直進しないと、高速の入り口にはたどり着かない。滅多に走らない道で右折するタイミングがよく分からない。
前を走る車につられたのか、気づくと、福岡空港のターミナル。1周しただけでは外に出れず、2周した。ハハハハハー!
北九州から戻り、高速を下りれたが、その先が分からなくなった。直進していると、やがて、『この先、北九州』の看板。ア~~~!また、北九州へ行こうとしていた。
今も、方向音痴は変わらない。グーグル・マップで念入りに目的地までのルートをチェックするが、1つ手前の交差点で曲がったりする。「こっちかなぁ…」という感は、当たったためしがない。ルートを覚えるには、数をこなすしかない!よね?
さて、おまけの話。
ツボ取り動画の編集をしようとしたら、ない!ない!ない!撮ったはずの動画の一部がない!間違って消しちゃった?自分で編集するので、消したのは自分だけど…ど…ど…。もう1度撮り直す?す?す?それしかないけどーっと、行き場のない気持ち…。
福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。