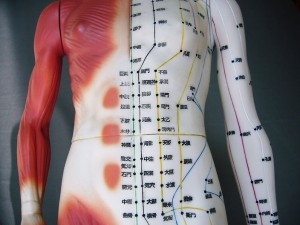東洋医学では、この世の中のすべての事物は『陰』と『陽』に分けられ、
両者は対立しあい、制約しあう…と、とらえています。
さて、ここで問題。
『上』は、『陰』でしょうか? 『陽』でしょうか?
『上』は、『陽』。 『下』は、『陰』。
『右』は?
『右』は、『陰』。 『左』は、『陽』。
『男性』は、『陽』。 『女性』は、『陰』。
(どうしてって、つっこまないように…)
体に張り巡らされている経絡(けいらく)もしかり!
陰の経絡と陽の経絡があります。
腰痛治療でよく用いられる、『足太陽膀胱経 あし・たいよう・ぼうこうけい』。
この経絡の始まりは、目頭と鼻の間にあるツボ、『睛明 せいめい』。
おでこ→頭頂→後頭→うなじ→背骨の横→お尻の中央→太ももの後ろの中央
→膝裏→ふくらはぎの中央→外くるぶし。
そして、足の小指の外側にあるツボ、『至陰 しいん』で終わります。
すべての経絡の中で、一番長い!
この経絡の上にのっているツボは片側67個。
左右合わせて134個!
鍼灸治療では、この経絡の上にのっているツボを使って、
経絡の流れを良くして、腰痛を改善します。

これは、ツボ・モデルの背中。
背骨の外側の2本の黒線が、足太陽膀胱経。
このツボ・モデルは左しか経絡が描いてありませんが、
もちろん右側にも対称的に2本あります。
腰痛治療には、腰のツボを使いますが、
脚のツボもよく使います。
名前からしてわかるように、『陽』の経絡。
この経絡には、『陰』の経絡の相棒がいます。
『足少陰腎経 あし・しょういん・じんけい』。
この経絡は、足の裏にあるツボ、『湧泉 ゆうせん』からスタート!
内くるぶし→膝の内側→太ももの内側→おなかの中央近く→胸の中央近く。
そして、鎖骨内側の下にあるツボ、『兪府 ゆふ』で終わります。
この経絡の上にのっているツボは片側27個。
左右合わせて、54個。
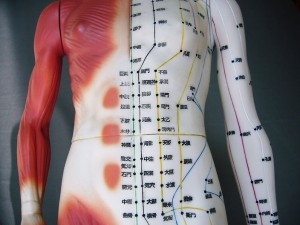
これは、ツボ・モデルの胸からおなか。
胴体中央の外側の黒線が、足少陰腎経。
先ほどの『足太陽膀胱経』とは、表と裏の同じ位置にあたります。
これらの『陰』と『陽』の経絡のバランスを整えることが、
東洋医学では重要となります。
私は、鍼灸師になる前は、理学療法士(リハビリ)をしていました。
西洋医学で腰痛を治すとなると…、
骨、筋肉、神経の状態の把握が重要となります。
リハビリ(=運動療法)で、アプローチできるのは筋肉。
痛んでいる腰の筋肉を温めたり、
ストレッチングで柔軟性を出し、
筋力をつけていく…。
このとき、『背筋』の相棒の『腹筋』のフォローも大事!
腰を痛める原因の1つは、背筋と腹筋のアンバランス。
腹筋が弱く、背筋(特に腰)ばかり働かせてしまうので、腰痛に…。
腹筋に力を入れながら、背筋を少しずつ緩めることにより、
私たちは滑らかに上体を曲げることができます。
反対に、上体をゆっくりと反らせるときは、
背筋を少しずつ縮めて力を入れ、
腹筋を少しずつ伸ばして力を緩めていきます。
表(腹筋)と裏(背筋)が協調して動けることが
腰痛治療の大事なポイントになります。
こんな見方をすると、
東洋医学と西洋医学って共通点があると思いませんか?
今月のお灸教室のテーマは、『腰痛』。
テキストを作りながら、こんなことを考えていました。
腰に自分でお灸をするのは難しいですね。
お灸教室では、モグサではなく、塩を使った塩灸もします。
パックの中に塩を入れて、電子レンジで温めます。
火を使わないので、腰に自分でしても安全です。
作り方は簡単なので、参加者の方と一緒に塩灸を作ります。
9月11日(火)と16日(日)に開催します。
興味のある方はどうぞご参加ください。
詳細は左のカテゴリーの『お灸教室のご案内』をご覧ください。
またまた、長いブログにつきあっていただきありがとうございました。
専門的すぎて、難しかったかなぁ~。
もうちょっとわかりやすく書けるように、修行しまーす!