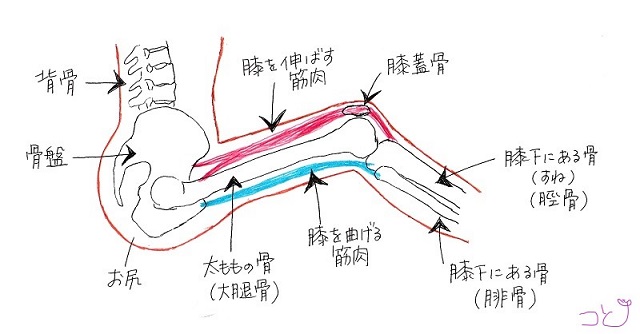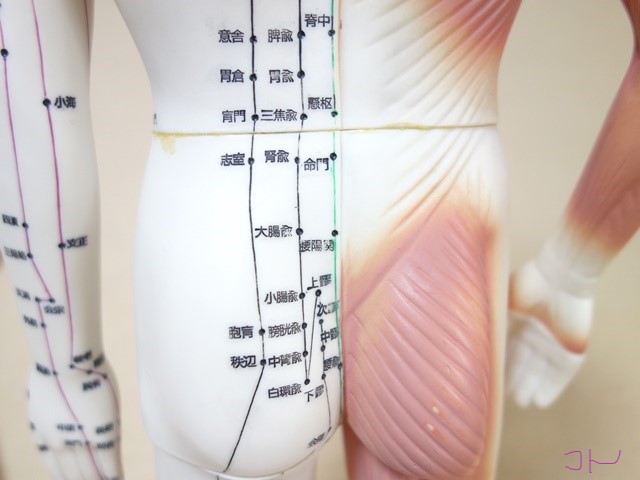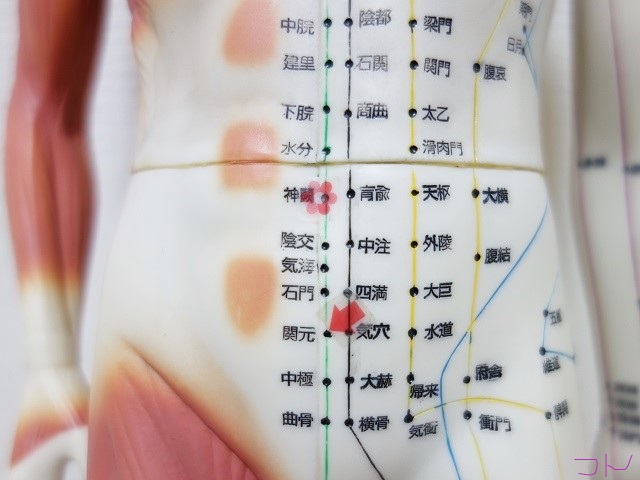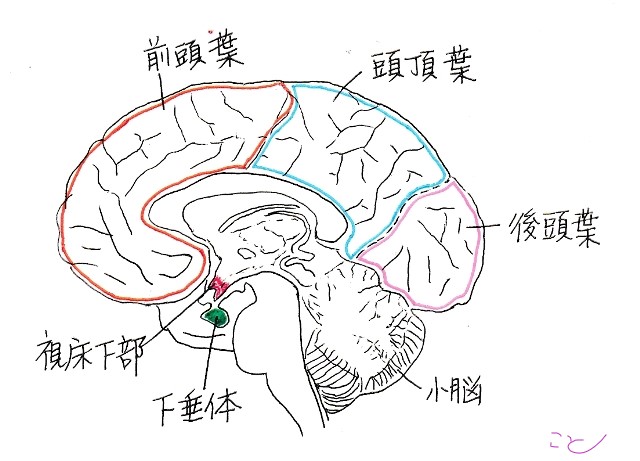【冷え症】セルフケア~『冷えに結びつきやすい生活習慣』の見直し
快眠のための『1日のスケジュール調整』
慢性疲労は、冷えに結びつきやすい。そのため、その日の疲れを、その日の睡眠でとっておきたい。
疲れがとれて、すっきり起きられる『睡眠時間』は、人それぞれ異なる。時計の目覚ましをセットしなくてもいい日に、セットせず、自然に目が覚める時間をチェック。何回か試してみると、自分の『ベスト睡眠時間』が分かる。
起床時間から睡眠時間を引くと、就寝時間が決まる。就寝時間から片付けなどの時間を引くと、夕食時間が決まる。
仕事が不規則だったり、家族がいると、自分の思い描くスケジュール通りにはいかない。でも、1日は24時間しかない。充分な睡眠時間を確保できなければ、仮眠や、心身がリラックスできる『すきま時間』を作ろう!
入浴は浴槽につかる
一人暮らしだけでなく、家族の入浴時間がばらばらだと、シャワーだけですませがち。
浴槽につかると、全身が温まり、冷えの治療や予防にもなる。体と心の緊張をほぐし、疲れもとれやすいよー!
エアコンを使いすぎない
人間の体には、外気の温度が変化しても、『体温を一定にコントロールする機能』や、『温かさを維持する機能』が備わっている。
エアコンの効きすぎた部屋に長時間いると、自分で体温を調節する必要がないので、これらの機能が衰え、低体温になることもある。

温暖化のため、一年中、気温の変動が激しくなった。室内に湿度つきの温度計を置き、エアコンの設定温度に気を配りたい。
また、エアコンは足元が冷えやすいので、サーキュレーターなどを併用し、空気を循環させよう。暖房を使うときは、加湿器も併用すると、乾燥を防ぎ、温かさが増す。
タバコは控える
タバコに含まれるニコチンには、血管を収縮させる作用がある。タバコを吸うと、全身の血流が滞り、体が冷えやすい。喫煙はできるだけ控えたい。
ストレスをため込まない
ストレスや心配事が長引くと、自律神経が乱れ、冷えを招きやすい。
好きな音楽を聴く、好きな映画を見る、友人とおしゃべりをする、美味しい物を食べる…など、自分の体と心が喜び、楽しめることがいくつかあるといいねぇ。
旅行など、ある程度の時間が必要なことだけでなく、すきま時間にちゃちゃっとできることがあると、ストレスをため込みにくいと思う。
コトーは映画が好きだけど、最近、ドキュメンタリー映画しか見に行かない。ちょっと気になる映画は、ドキュメンタリーではない。どうしようかなぁ…。
ネットで映画の公式サイトをのぞいてみた。監督と主演の役所広司(やくしょ・こうじ)さんが、小津安二郎(おづ・やすじろう)監督と俳優の笠智衆(りゅう・ちしゅう)さんの話をしている。笠智衆さんの大ファンとしては、行かねば~!
『PERFECT DAYS』を見に行った。令和の時代に、昭和が息づく映像。もしかして、トイレ清掃員のアルバイトをしていた?って思えるほど、馴染んでいた役所さんの演技。
「平山さん(主人公)だったら、こんなときどうするかな…と、自分の日常生活の中でも考えていた」と、役所さんの記事を読んだ。
ふと、落語家の柳家小三治(やなぎや・こさんじ)さんを思い出した。「落語家は、人を笑わせようと思っちゃいけない。落語に登場する人物になりきるだけだ」というようなことを自伝に書かれていた。
俳優も落語家も、登場人物がのりうつるくらいに、なりきることで、観客を感動させるんだなぁ…。
『鍼灸師・理学療法士コトー』の理想像は、鍼灸治療だけでなく、ちょっとした運動や日常生活の工夫をサポートして、治療に来られる方の健康と幸せに寄り添える治療家。
日常会話中、こんな風な話の展開にしたら、患者さんにより分かってもらえるかな…と気づく。「あれれ、前を歩いている人の歩き方が不自然。なんで、そう思うのかな…」と動作分析をしだす。日々の出来事で、『コトー』をレベルアップさせようとしている。
ありゃりゃりゃ、話がだいぶそれちゃった。次回は特集『冷え症』の最終回!【冷え症】体の中と外から温める鍼灸治療と予防鍼灸だよ~ん。
特集記事『冷え症』
【冷え症】セルフケア~『冷えに結び付きやすい生活習慣』の見直し
【冷え症】体の中と外から温める鍼灸治療と予防鍼灸
福岡県福岡市にある、女性専門鍼灸&パーソナルトレーニング≪レディース鍼灸ことうプラス≫の女性鍼灸師・理学療法士のコトーでした。